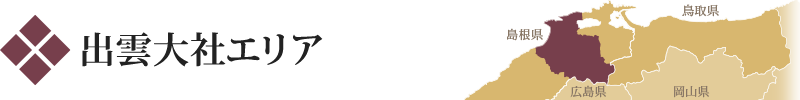
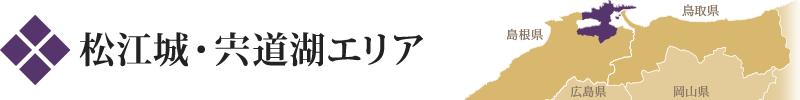


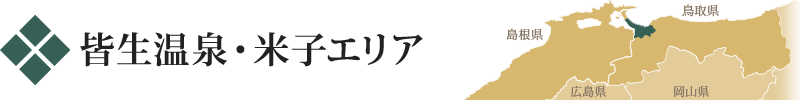
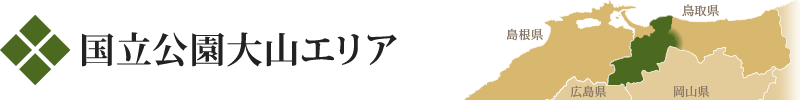
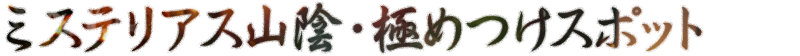
普門院(観月庵)

今から約400年前、松江藩の初代藩主である堀尾吉晴公が松江城を築城、城下町を造成したときに開創された寺院。遊覧船が優雅に行き交う松江城の堀川沿い、「普門院橋」を渡った先にあります。
当初は、豊国神社(祭神・豊臣秀吉公)として松江市西川津町市成に造営。慶長20年(1615年)の「大坂夏の陣」で豊臣氏が滅亡した後は禄を没収されましたが、第3代の堀尾忠晴氏が松江市寺町に移転、「松高山 普門院」と改称して造営されました。ところが、延宝4年(1676年)に起こった大火により焼失してしまいます。再建されたのは元禄2年(1689年)のことで、松平家第3代藩主・松平綱近公が松江城の鬼門となる現在の場所に移り、今日に至っています。
コチラでの見どころは、境内にある「観月庵(かんげつあん)」。享和元年(1801年)に建てられた細川三斎流の茶室で、第7代藩主であり、茶人として「不昧流」をたてた松平不昧公もたびたび訪れたといわれています。また、明治時代この松江で暮らしていた小泉八雲も、ここでお茶の手ほどきを受けたことがあるそうです。
飛び石伝いに庭を歩いていくと、庵に併設されている「腰掛待合」に着きます。観月庵と共に市の文化財に指定されているもので、天井には宍道湖のシジミ漁に使われていた舟板が利用されています。
庵のにじり口を入ると、二畳隅炉と四畳半が組み合わさった本席が。東側には天井まで開いた大きな窓があり、腰なし障子2枚が建っています。不昧公は、床前に座し、障子を開けたこの窓から東の空に昇る月を眺めるのが好きだったとか。また、庭には池があり、その池に映り込んだ“もう一つの名月”を望むことも。不自然なほど大きな窓だからこそ、月と庭が醸し出す情緒をより深い味わいで感じることができるというわけなのです。音もなく昇る月、月明かりに照らされた庭、耳に優しく響く葉音や虫の声……。この庵では抹茶を頂くことができるので、不昧公も感じたであろうそんな風情と共に味わってみてはいかが?
茶の湯の世界に触れ、気分がよくなったところですが、普門院にはゾッとするような昔話が残っています。それは、小泉八雲の著作『怪談』に登場する「小豆とぎ橋」のお話です。
【小豆とぎ橋のあらすじ】
普門院の近くには、その昔「小豆とぎ橋」という橋がありました。この橋には、夜な夜な女の幽霊が現れ、橋の下で小豆を洗っているという言い伝えがあり、この場所で謡曲「杜若(かきつばた)」を謡いながら歩くとよくないことが起きるので、決して謡ってはならないとされていたそうです。
ある日、この世に恐ろしいものなどないという豪胆な侍が、「そんなばかなことがあるか」と「杜若」を大声で謡いながら橋を通ったのです。「ほら、何も起こらないではないか」と笑い飛ばしつつ侍が家の門まで帰り着くと、すらりとした美しい女に出会いました。女は侍に箱を差し出し、「主からの贈り物です」と告げるとパッと消えました。いぶかしく思った侍が箱を開いてみると、中には血だらけになった幼い子どもの生首が! 仰天した侍が家へ入ると、そこには頭をもぎ取られた我が子の体が横たわっていたのでした……。
背筋が凍るような怪談ですよね。今はもう「小豆とぎ橋」はないので幽霊が現れることはないと思いますが、松江城を取り囲むように流れる堀川を遊覧船に乗って巡ると、この普門院橋をくぐった先の川土手で、ふいに女の幽霊のレリーフが現れるとか。本当かどうかは遊覧船に乗ってみてのお楽しみ。
| 0852-21-1095 | |
| 島根県松江市北田町27 | |
| 9:00〜16:00 | |
| 毎週火曜日 | |
| あり | |
| JR松江駅より松江レイクラインで塩見縄手バス停下車、徒歩約10分 | |
| https://matsue-fumon.jp/ | |
| 拝観料のみ 300円 お抹茶付き 800円 | |
| ※悪天候・行事等により拝観時間の変更やお休みをいただく場合がありますので予めご了承ください。 ※季節によりお菓子は異なります。 ※冬季1、2月の拝観は要予約(年末年始:休観とさせていただきます) ※学校単位での拝観は、事前の連絡をお願いします。 |

 出雲観光ガイド
出雲観光ガイド
 水の都松江 松江観光協会公式サイト
水の都松江 松江観光協会公式サイト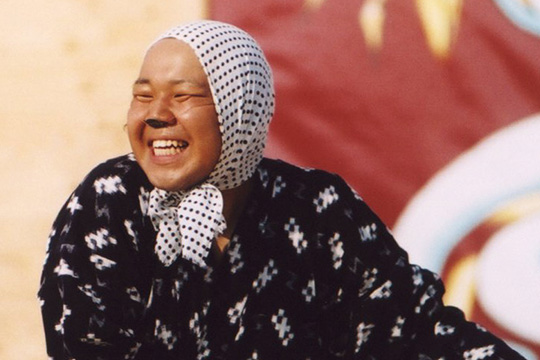
 安来市観光協会公式サイト
安来市観光協会公式サイト
 さかなと鬼太郎のまち 境港市観光ガイド
さかなと鬼太郎のまち 境港市観光ガイド
 米子観光ナビ
米子観光ナビ
 南部町観光協会
南部町観光協会


松江城の鬼門を守り続けて300余年
寺院内の茶室は不昧公も愛した名月の庵